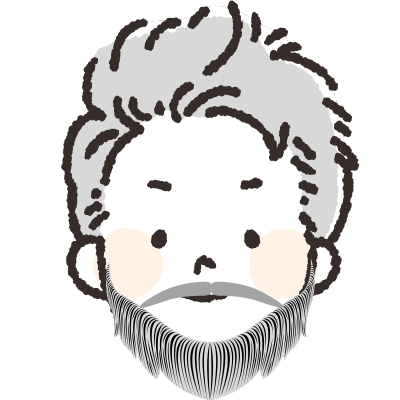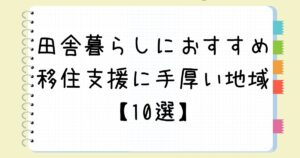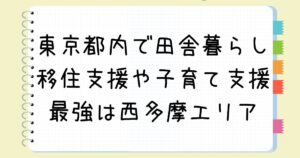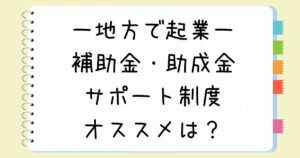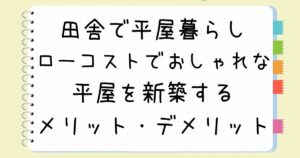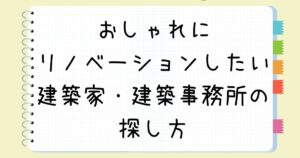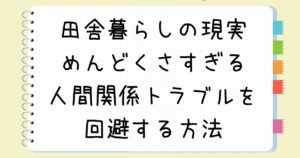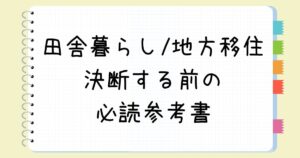地方に行くと、使われていない「田んぼ」や「畑」「果樹園」を沢山目にします。
中には、雑草や雑木だらけで荒れ放題で、見るも無残な土地もあれば、放棄してからまだ間もないのか、季節になると果樹がたわわに実ったままの果樹園もあります。
高齢で畑仕事が出来なくなって放置されてるんだなあ、後継者もいないんだなあ、と思う一方で、地方に移住して農業をやりたい、家庭菜園をやりたい、という人は少なくないのだから、使っていないのなら安く譲ればいいのに、貸せばいいのに、と思うのですが、それをさせない仕組みになっています。
農地は買えないってホント?(ホントです)
日本では、”農業(農家)を保護する“目的で、農地法という法律により、非常に厳しく規制されています。
農地は自由に売買できないってホント?(ホントです)
原則として、農地は自由に売買したり譲渡したりすることは認められていません。
売る相手(買主)が農家であることが絶対条件です。
故に、
・サラリーマンは農地を買えません
・自営業(個人事業主)でも自由に農家になれません
・資産に余裕があっても、農家でなければ農地は買えません
・移住希望者でこれから農業やりたいです、という人も買えません
農地を買うことができるのは、「その農地を管轄する農業委員会に許可を得た農家」もしくは「農業従事者」のみなのです。
農地付きの家は買えないってホント?(条件付きです)
空き家バンクや、中古物件情報サイトでは、田舎に広大な、あるいはほどほどの農地付きの格安物件もあります。
家付き・農地付きのセット販売ですが、「農地」は「農地」です。他の中古物件のように、代金を支払えば簡単に購入できるわけではありません。
家と農地のセット売りであっても、農地の売買には農業委員会への申請と許可が必要です。
農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)
農地法第3条(農林水産省)
農業委員会から許可を受けるには、いくつかの条件があります。
- 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
- 農地の取得者が、必要な農作業に従事(原則、年間150日以上)すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
「営農計画」とは、事業計画の農業版。
【営農計画とは?】
育てる作物を決め、およそ5年先までの生産計画、販売計画、資金計画といった、農業を経営するための計画を立て、就農計画書・営農計画書として提出します。
この準備は自力でもできなくないようですが、その農地を管轄する農業委員会やJAなどに相談するのが、オススメです。
農地は相続も大変
家族などに相続する場合であっても、その相続人が営農を続けなければ「農地」のままにしておくことができません。
その場合(相続人が営農しない)は、
・農地のまま農業従事者に売却する
・農地を宅地や雑種地等に変更=農地転用する
ことになります。農地をそのまま放棄すると、相続税にも関わってきます。
通常、この農地転用許可制度(正式には、農地法第5条による許可申請(届出))を利用して、農地を宅地に転用し、売買することになります。
農地ではなく宅地になることで、一般的な不動産と同じように、誰もが自由に売買または譲渡することが可能になります。勿論、不動産業者に仲介をしてもらうことも可能です。
しかし、すべての農地で転用が認められるわけではありません。基本的には農地の種類と、その転用理由(利用目的)によって判断されます。
○認められるケース
今後市街化が進む可能性の高い地域の農地(第二種農地、第三種農地)
×認められないケース
第二種農地、第三種農地以外の全ての農地(農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地など、今後も農地であるべきとされる土地)
農地の種類は、その農地を管轄する農業委員会に確認が必要です。
転用の許認可の判断は、その農地を管轄する農業委員会が行い、都道府県知事が許認可を経て、最終的には法務局が許可することで成立します。
農地転用は、その手続きも判断基準も複雑で曖昧です。そして数年単位で時間がかかる場合があります。農地転用の許可に詳しい行政書士に相談する必要があります。
農地は普通に借りられないってホント?(ホントです)
農地を借りるにも農業委員会の許可が必要
農地の購入と同様に、農地を賃貸住宅のように簡単に借りることはできません。
売買と同様、その農地の管轄の農業委員会の許可が必要です。
農地を借りる裏技ないの?
農地を借りるのではなく、農地の維持管理を請け負う「農業代行」や「委託」という形で、利用することはできます。
賃貸借契約を結んだことが、農業委員会にバレると面倒なことになります。
借主は、地代を支払う代わりに委託料等をもらうか、契約内容によっては貸主が委託料を支払う代わりに、対価として収穫物の権利の権利を借主に譲るといった、ビミョウなこともできます。
| 農業代行・委託サービス | 農地賃貸借 | |
|---|---|---|
| 農作業をする人 | 代行者 | 借り主 |
| お金の動き | 所有者→代行者へ手数料 | 借り主→所有者に賃借料 |
| 収穫物の権利 | 農地所有者 ※ 契約次第で変更可 | 借り主 |
| 農地維持管理や草刈り | 農地所有者 ※ 契約次第で変更可 | 借り主 |
| 水利組合等への参加 | 農地所有者 ※ 契約次第で変更可 | 農地所有者 ※ 契約次第で変更可 |
| クレーム等対応 | 農地所有者 ※ 契約次第で変更可 | 借り主 |
| 災害時の復旧負担 | 農地所有者 | 借り主 |
| メリット | ・農地の権利が残る ・契約次第で変更できることが多い | ・草刈りはしなくてもいい |
| デメリット | ・農地に関わる義務や責任が残る ・手数料次第では利益が少ない | ・農業委員会の許可が必要 |
農地を花畑にしてはダメってホント?(ホントです)
農地は農業以外の目的で利用することは認められていません。
農地に家を建てるのは勿論、駐車場にしたり花畑にするのもNGです。
花畑はNGですが、販売用の花木栽培ならOK。農地は原則農作物の栽培以外はしてはいけないことになっています。そして、どのように利用するのか(何を植えるのか)は農業委員会の許可・確認が必要です。
以前移住した敷地に隣接する広大な土地が、長く耕作放棄された荒れ放題の農地でした。そのままでは見た目が悪いので、草刈りをし整地し花を植えたら、農業委員会に怒られたことがあります。
そもそも無断で、しかも農家でない人が他人の農地を整備するなんて、、とけんもほろろでした。どんなに放置されていても農地は聖域なのです。
なお、その農業委員会様は、その奥にあり別の所有者が竹林にならないよう、年に数度手入れをしている農地に、とある花が咲き乱れているのを指さし、「農地はあのようにするものだ」とおっしゃいました。
残念ですが、それは満開のソバの花ではなく、草刈りされた耕作放棄地に咲いたヒメジョオンというただの雑草でした。。。
花壇はダメでも、農地に雑草が咲き乱れることには何の問題もありません。
管轄地の農業委員会と皆々さまと仲良くしないと、どうでもいいとばっちりをうけることもあります。
農業委員会とは何者?
ところで、農業委員会とは何者なのでしょうか?
農業生産力の向上と農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与することを目的として、市町村に設置されている行政委員会。従来の農地委員会・農業調整委員会・農業改良委員会を統合したもので、昭和26年(1951)の農業委員会法に基づく機関。農地の利用関係の調整、技術の改良・普及の指導、行政庁への建議あるいは答申などを行う。
コトバンク
この組織(仕組み)があることで、守られるものと、失うものがあります。私は失うもののほうが多いように感じています。
空き家が増え、耕作放棄地が増え、里山の景観は荒れ放題。生態系にも影響が出始めています。