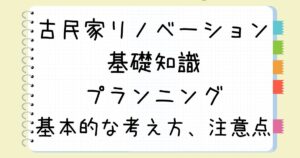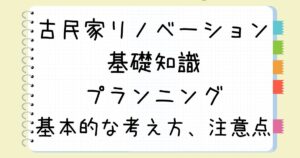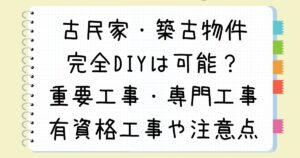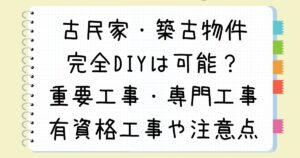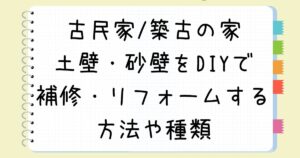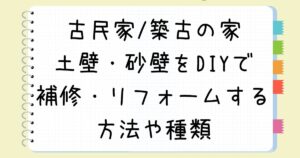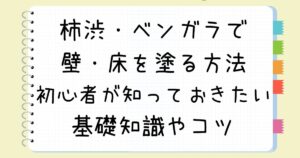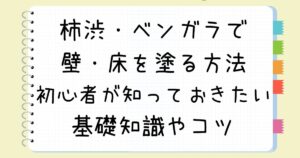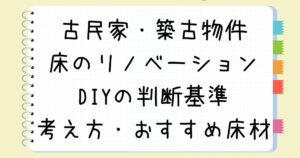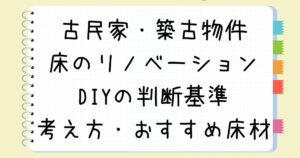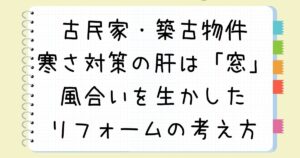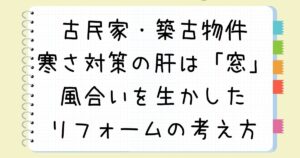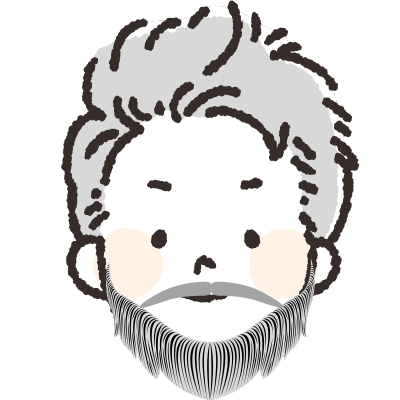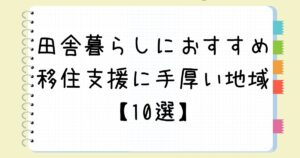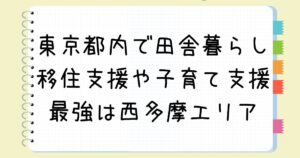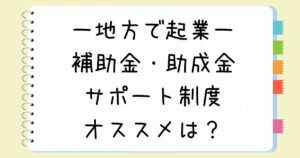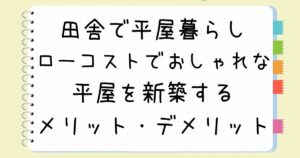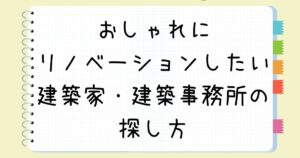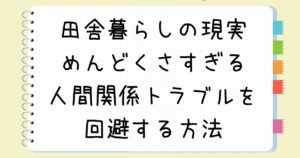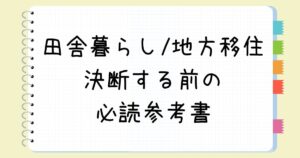田舎にある格安物件・古民家・築古物件・ボロ小屋などは、そのまま住める程度に維持されている、リフォームされている物件は稀です。
多くの物件は、設備の劣化はもちろん、構造にも手入れが必要なレベルであり、加えて前の住人の暮らしがそのまま残っていることも珍しくはありません。
設備交換、クロス貼り直し程度のリフォームで済めばいいのですが、間取り含めて大掛かりな改装=リノベーションが前提であれば、住宅設備はもちろん、床・壁なども解体します。
場合によっては、建物の構造上必要な梁や柱だけを残して、他ほとんど全てを解体することもあります。
解体はリノベーションを始める儀式
安く買って、あるいは借りて、好きなように、且つ、資産価値ゼロだったものを価値ある物件にリノベーションする、これが田舎暮しの最初の楽しみであり大仕事。そのスタートとなるのが解体です。
解体は、リノベーションを始める儀式でもあるのです。
格安物件・古民家・築古物件・ボロ小屋をセルフリノベーションする場合には、解体も自ら行うことになります。
もちろん、業者に頼むことも可能です。ただ、壊す・解体することは誰にでもできる作業である一方、なかなかあり得ない貴重な体験にもなります。
家の構造を知る上でも、とても役にたつ作業です。
あまりのカビ臭さやほこり、ゴミなどにゲンナリすることもありますが、基本的には壊せばいいのですから、楽しい作業です。快感です。
古民家解体と廃材処理を自分たちでやる方法
古民家・築古物件・ボロ小屋 解体の準備
先ずは、古民家の解体作業を自分たちでやる場合のざっくりとした手順です。
【事前準備】
- どこを壊すか計画する
→ 壊す箇所、再利用したい物に印をつける - 参加人数と日程などの予定を組む
- 手伝ってくれるメンバーを集める
→ 解体の範囲にもよりますが、少なくても2〜3人いると安心です - 道具を揃えておく
- 残置物などがあれば、必要に応じて解体前に処分しておく
- 電気工事が必要な場合には、電気工事士の資格を持った人に依頼する
- 上下水道、ガスの配管などに関する作業は専門業社に依頼する
【当日】
- 人数分の道具と食べ物・飲み物を用意する
- 解体する手順・役割分担を確認する
→ 壊す順番、残す箇所、再利用したい物の確認 - お神酒と祈りを捧げ解体を始める
→ 本格的にやる場合は地元の神社に依頼する - 解体する
- 廃材を区分して集積する
- 養生する
→ 躯体は勿論廃材も剥き出しのままにしない - 廃材の処分
→ 当日に持ち込めない・回収がない場合には、ブルーシートなどで養生しておきます - 参加者に謝礼を渡し解散
→ 日当〜取っ払いが基本です
家の解体は、ひとりでも不可能ではありませんが、複数人いる方がいいです。
なお、自宅であっても、電気配線に関する作業は、第二種電気工事士等の資格が必要です。
公共の上下水道、プロパンガスの配管などに関する工事は、専門業社に依頼しなければなりません。
壁や柱には、壊していいものと、壊してはいけないものとあります。完全に解体するのであれば構いませんが、リノベーションの場合には、住宅の構造などの基礎知識が必要です。
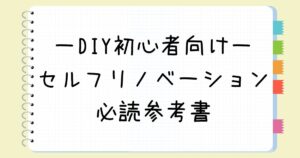
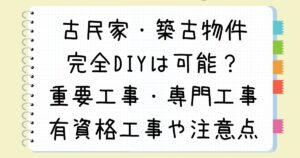
古民家解体に必要なもの

床・壁等の解体といっても、それなりに必要なものがあります。
都市部で暮らしていると必要のないものばかりですが、田舎暮らしでは必要な道具です。今後も使う前提で揃えておくといいでしょう。
- 安全靴
- ヘルメット
- ゴーグル
- マスク
- 手袋
- ハンマー
- 釘抜きハンマー
- バール
- 電動のこぎり
- のこぎり
- 脚立
- ブルーシート
- ゴミ袋(ガラ袋)
ホームセンターでも揃います。
Amazonなどの通販で購入する方が楽ですが、不慣れな方はホームセンターなどで現物を確認することをオススメします。
道具の大きさ、重さ、持ち手などで、作業のしやすさや体への負担が変わります。

私は、一緒に作業したチームと同じ工具や道具(結構本格的、、)を使用していましたが、妻は「重い・デカい」と、自分用の軽くて小さめの工具などを買い直していました。
慣れている人が使う道具・工具は、パワーもあり作業効率はいいですが、不慣れな方、腕力・握力に自信がない方は、現物を確認して選ぶことをオススメします。
解体後の廃棄物処理
解体した後の廃棄物の処理も、自分たちですることが可能です。
自分たち、つまり家主や同居家族で解体して発生した廃材については「一般廃棄物」扱いとなり、自分たちで処分場に搬入し処分することが出来ます。
処分場まで運ぶ手段は何でも良いです。
乗用車でもいいわけですが、積載量的に無理だし、汚れたり傷ついたりします。トラックをレンタルして運びましょう。最大積載量2トン未満なら普通免許でOKです。
廃材処理を業者に委託する場合は、「建築廃材」扱いとなり処分方法が変わります。地域毎に指定業者が決められていますので、そちらも物件住所の行政機関にお問い合わせください。
古民家解体と廃材処理を業者に依頼する方法


解体は面白い、けれど危険が伴う作業です。廃材処理も厄介です。
中途半端になりそうでしたら、最初から専門業者にお願いしましょう。
業者に依頼する場合は、解体の窓口で無料で見積もり比較が出来ます。
東証上場企業が運営、独自の審査基準を設けそれにクリアした優良業者しか紹介しないので安心です。基本的に物件近くの業者が複数紹介されますが、物件の場所によっては選択肢が無い場合もあります。
いずれの業者に頼むにせよ、この手の見積もりはシロウトには判りにくいので、以下を事前に頭に入れておき、不明点や不備があれば必ず発注前に確認するようにしましょう。
古民家解体を業者委託した場合の費用(相場)
一軒家の解体費用の相場は、家の構造によっても異なります。
【一軒家の解体費用相場】
- 木造:3~5万円/坪
- 鉄骨造:5~7万円/坪
- RC(鉄筋コンクリート)造:6~8万円/坪
上記は、解体し更地に戻す場合の概算金額です。建物本体の解体、廃棄物処理費用、整地費用などが含まれます。
リノベーション前提の場合、全てを解体し更地に戻すわけではなく、基礎や躯体は残りますので、また費用は異なってきます。
【解体費 内訳参考】
- 人件費:1万5,000円~2万円/人
- 仮設工事(養生シート込み):500円~1,500円/㎡
- 基礎解体:3,000円~6,000円/坪
- 内装解体:5,000円~1万5,000円/坪
- 屋根解体:1,000円~5,000円/㎡
- 重機解体:3,000円~10,000円/坪
- 樹木撤去:1万円~4万円/本
- ブロック塀の解体:3,000円~5,000円/㎡
- 廃棄物処理:6,000円~2万5,000円/㎡
- 重機運搬:4万円~5万5,000円
- 諸費用:5万円~10万円
物件の構造、解体する範囲によっても異なりますし、地域や立地条件によっても変わってきます。遠方僻地であればその分高くなります。無論、工事期間が長くなれば長くなるほど高くなります。
また、廃棄物の処理費用は、廃棄物の量は勿論、種類でも異なります。その単価は地域によっても異なりますので、実際に物件の見積もりを取ってみないとわからないものなのです。
更に、それらとは別途、以下の費用が発生します。
家財・残置物の処分
基本的に、解体工事を通して出た産業廃棄物に関しては、解体業者が責任を持って処分することになりますが、最初から家の中に残っていた家財や残置物がある場合は、その処分費用は別途かかります。
事前に、買取業者に買い取ってもらったり、粗大ゴミ・臨時ゴミとして、物件所在地を管轄するクリーンセンター(行政が運営するごみ処理施設)に持ち込むことで安く上がります。



賃貸オーナーをしている知人は、購入した空き家の使えそうな家具や残置物をトラックで自宅に持ち帰っていました。程度/状態がよく、自分の許容範囲であれば、再利用なども可能です。
アスベスト処理
築古物件であれば、アスベストを使用していることもあります。
アスベストが含まれていることがわかった時点で、アスベストの除去工事が必要となります。解体は除去工事後となりますので、追加の作業代や工期延長で追加費用が発生します。
家屋以外の解体工事
田舎の家では、家屋以外にも納屋、倉庫、別棟があったりもします。しばらく放置されていた物件であれば、庭や樹木など手入れも必要になります。
家屋本体以外の解体撤去費用は、基本的に別料金が発生します。
作業の範囲を明確にし、見積もりに含まれているのかは、契約前によく確認しておきましょう。
隣家との距離が近い場合
隣家との距離が近い場合は、解体する際に飛散する破片やほこり、ゴミなどによる損壊や汚れを防ぐため、また、騒音防止のため十分な養生を設置することとなり、追加費用が発生します。事前に確認しましょう。
重機が入れない場合
解体現場の前面の道路がとても狭い、隣家との距離が近いなど、何らかの理由で重機が解体現場に入れない場合は、重機を使った解体工事を行うことができません。
全てが手作業となることで、工期が長くなり、人件費も嵩みますので、費用が高くなることがあります。
また、解体後に出る廃材運搬用のトラックが入れないとなると、現場から離れたところに駐車スペースを確保しなければならず、別途費用が発生します。
他にも、大きなトラックであれば、1回で済む搬出が、小さめのトラックで複数回搬出する必要があれば、その分費用もかかります。
地中に障害物などがあった場合
瓦や木材、コンクリートや浄化槽、防空壕や岩、古井戸や廃材、その他のゴミや基礎など、何らかの障害物が地中にある場合は、その撤去作業で費用が別途発生します。
基本的に家屋や建物を解体する際は、地中1m~1.5mに障害物などの不要なものが埋まっていないか確認するのが普通ですが、工事を進めていかないとわからない部分もあります。
また、土壌汚染が発見される場合もあり、その場合は汚染土処理にかかる費用も負担する必要があります。
古材を再利用する場合
古材の再利用を行う場合も追加料金の対象です。
一般的な解体作業とは異なる作業が発生するからです。
再利用する木材などは、壊さないように解体する、廃棄するものとはわけて保管するなど、手数が大きく変わるからです。
また、古材を買い取ってもらう目的であれば、傷をつけないように古材を取り出すなど、なおさら慎重に作業を行う必要があり、費用は高くなります。
何かとお金がかかる解体作業ですが、古民家解体の補助金制度もあるようです。うまく利用すれば、多少なりとも金銭的負担は減ります。↓
▼参考記事
https://rural-life.jp/kominka-hojokin
解体という作業を楽しめるか、楽しめないか、お金を節約するか、時間と労力を節約するか、お金で解決するか、選択はあなた次第です。
自ら解体するか業者に頼むかで、費用はかなり違ってきます。
物件が小規模、解体する箇所が小規模/部分的な場合は、時間も労力もさほどかかりませんので、自ら解体することをオススメします。
尚、事前に建築家など専門家とリノベーションプランを立て、そのプランに合わせて解体するようにしましょう。
建築家によっては解体手順をアドバイスしてくれたり、解体作業を面白がって手伝ってくれる場合もあります。
また解体や廃棄物処理に詳しい人もいるので、何でも相談できる良き専門家に知り合えると、古民家リノベーションは俄然楽しくそしてスムースに進んでいきます。